子供達の幸福な未来の為の教育
子供達の生来が幸せなものになる為に、人生の計画「ライフプラン教育」を今以上に進めて行く必要がある旨、強く要望した。
議場で主張した議論の概要は次の通りである。
詳細はその後に掲載する。
概要
10代から60代まで広い世代に於いて幸福な生活には、配偶者の有無、子育ての満足度が大きく影響を及ぼす。
教育指導要領を見る限り中学生では性の抑制しか教えず、高校になって初めて性と家庭に関して記述があり、異性に対する責任、子どもを持つ事の責任が教えられる事になるが、十分ではない。
三重の子供達のアンケートで8割近くの生徒達がいずれは子どもを持ちたいと考えている。どのように子を産み、育てる事が将来の幸福な生活を作るのか教える事は重要な事である。
男性が育児や家事に積極的に関わる事が、二人目以降の子どもを持ちたいと思う意欲に繋がるという報告を挙げている。
逆に望まない妊娠による出産は、子どものネグレクトや虐待死と大きく関係しているという報告が出されている。
県の相談員によると、10代の子達があまりにも稚拙な性に対する知識しか持って居らず、それが原因で妊娠をしており、今以上に早い段階から性と家庭、家族計画における男性と女性の考え方、正しい知識を教えていく必要があると訴えている。
子ども福祉部がライフプラン教育のための冊子を中学生向けに作成しており、これの積極的活用を求めた。
答弁として
市町の教育委員会の健康教育担当者が集まる会議で冊子を紹介し、既に活用している中学校の取り組み状況を紹介するとの答弁が、教育長からあった。
詳細
国が行った生活の質に関する調査がある。(同調査へのリンク)
ここから幾つか引用する。
男性女性共に、どの世代に於いても配偶者がある事と幸福度に明確な関係性が表れている。
配偶者との接触頻度も幸福度に大きな影響を与えており、頻度が高いほど幸福度が高い。
60代で20才以上の子どもが居る人達の幸福度が最も高く、30代、40代では子どもがいる人達は、子どもがいない人達よりも幸福であり、6才未満の子どもを持つ人達は世代を問わず幸福である。
過去及び現在の子育ての満足度も幸福度に大きく影響を及ぼしている。
ただ、10代20代のまだ小さな子どもをもつ親は、子育てが常に楽しい、ないしは楽しいと答えた数は全体の半数を割っており、どちらでもないと答えた数が多数を示している。
これは子どもに手がかかるうちは子育ては大変である事の表れである。夫婦が協力して子どもを育て、大変な時期を乗り越えて行く事が、その後の幸福な生活を送るために重要な要素だという事が分かる。
教育指導要領を見ると、中学生の保健体育では、性衝動の抑圧、性感染症の危険性、避妊具の使用の指導しか記述されていない。
高校生の保健体育科でやっと、思春期と健康、結婚生活と健康などの記述が出てくる。責任感を養い、異性を尊重する態度が必要とされ、解説に受精、妊娠、出産とそれに伴う健康に関する理解、家族計画の意義など性と妊娠に家庭という事が関連付けられて教えられる事になる。
避妊具を使用する事で、人工的に妊娠を回避することができることは事実だが、本質的に性行為によって人は子を宿すわけで、その現実を理解した上で子どもを生育する環境を整え、妊娠し、出産し、生育すること、こそが高校の指導要領に書かれている養うべき責任、親の子に対する責任だと考える。
また、男女相互にその現実を理解し、妊娠、出産、育児への役割を担っていく心構えこそが教えられるべき異性への尊重なのではないか。
子ども・福祉部が作っているライフプラン教育のウェブページには、いずれ子どもが欲しいと回答している生徒が56.87%が、26.12%が分からない、明確にいいえと言ったのが17.01%だとするアンケート結果が掲載されている。
分からないと答えた17%を按分すると、77%の子どもが子どもを持ちたいといずれ考えるのだとすれば、
国の男女共同参画会議の報告では、男性の育児、家事への参加が少子化対策で有効で、第2子以降の子が多く生まれており、女性の負担が軽減され、夫婦の満足度の向上を通じて、子どもを産み育てていくことの意欲が高まるとかかれている。
シカゴ大学の山口一男社会学教授の論文では、会話を通じた妻と夫の悩みや楽しいことの共有度は、出生意欲に強く影響する。妻と夫の心理的共有体験度は出生意欲を高めると書かれている。
(同論文へのリンク)
夫が自分の悩みや楽しいことを妻と共有するのではなく、妻が自分の悩みや楽しいことを話すこと、夫が受け止めていると妻が認識しているか否かが重要である。
配偶者との接触の頻度が多いほど幸福感が高い。これは国の調査とも合致している。
逆に、夫婦間の関係がうまくいかなかった場合、あるいは子どもを産むことの準備ができていない男女が子どもを妊娠したときにどうなるのか。
労働政策研究・研修機構のつくったシングルマザーの幸福度、健康と経済的ウエルビーイングという論文では、(同論文へのリンク)
日本の母子世帯のほとんどは離婚によるものである
結婚しているカップルの3組に1組が離婚している
日本のシングルマザーは高就職率低収入である
離別した父親から養育費を受けているシングルマザーは2割に満たない
そしてシングルマザーの厳しい経済状況は、
彼女たちの精神的健康を低下させる要因の一つであり
全離婚の件数の6割に未成年の子どもがおり
その8割以上で母親が全児の親権を持っている
と書かれている。
これは夫婦間の関係が上手くいかなかった場合、子どもの生育環境が悪化する可能性が高い事を示す。
令和3年に公表された子どもの虐待による死亡事例等の検証結果には
ネグレクトが虐待の死因となった子供達の母親のうち、
予期しない妊娠、計画していない妊娠が一番で36.7%
母子健康手帳の未発行が30.2%
10代の妊娠が22.6%
ゼロ日児、即ち生まれて直ぐに死亡している事例では
母子健康手帳の未発行が78.8%
予期していない妊娠、計画していない妊娠63.5%
10代妊娠が28.8%
これは、子どもの命を守るため、子どもを産む事の準備が出来ていない男女が子どもを妊娠するケースを減らす必要がある事を示す。
三重県の電話相談では昨年LINEで160件、電話で200件の相談を受け、
半数以上が20代、LINE相談はほぼ全員が10代だった。
相談者はあまりに稚拙な性に関する知識しか持って居らず、その事が原因で妊娠している。
現場の方々や、ライフプラン教育の冊子を作成した産科医さんが、もっと早い段階から性と家庭、家族計画における男性と女性の考え方、正しい知識を今以上にしっかりと教えていく必要があるという切実な意見が出ている。
以上
単に性感染症の予防や避妊の必要性だけではなく、男性、女性のそれぞれの役割及び相互に責任を持つこと、いかに家庭を築いていくべきか、正しい知識と責任ある行動こそが自分たちの未来を幸せな夫婦生活、楽しい子育て環境をつくることにつながるということを教えるべきだと考える。
第一子の子育てが幸せである事が第2子以降を望むかどうかにとって重要である事から、少子化にとっても有意義ある。
また、望まない妊娠による児童虐待及び虐待死、あるいは離婚から来る貧困、ストレスといった不適切な養育環境から子どもを守ることに繋がる。
子ども・福祉部が作成して提供している「思春期のみんなに考えてほしいライフプラン」という中学生向けの冊子を今以上に活用し、中学生にも家庭の在り方と人生設計を積極的に教えるべきだと考えるが、現在までの取組状況とこれから拡充していく考えがあるかどうか、教育長に伺った。
答弁として教育長から以下の回答があった。
令和3年度は、県内の公立中学校28校でパンフレットを用いた学習が行われた。
希望する中学校が適切に活用できるよう、市町教育委員会の健康教育担当者が集まる会議などの機会に、パンフレットの紹介に加え、既に取り組まれている中学校での活用の仕方も含めて紹介することを考えている。







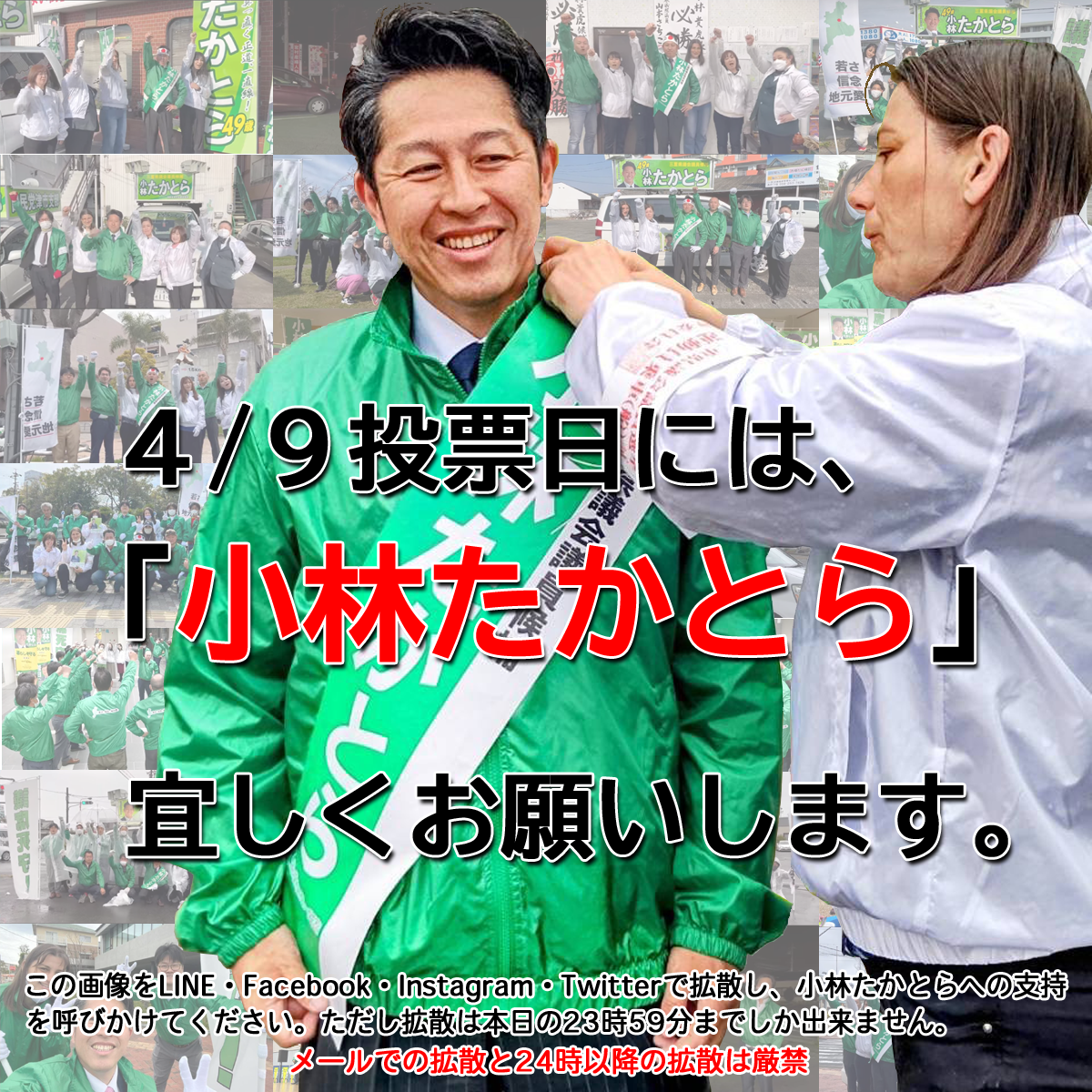
コメント
コメントを投稿